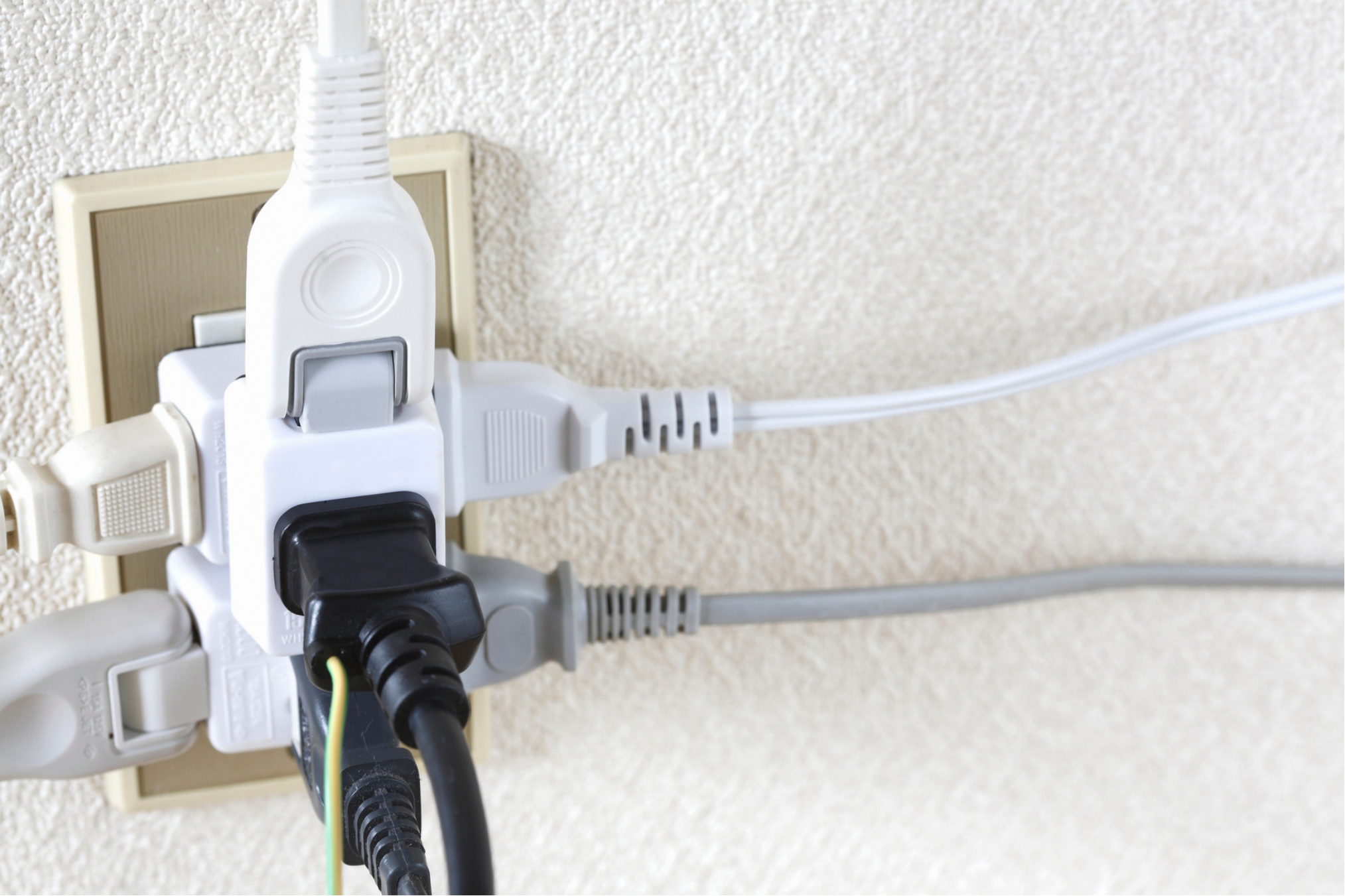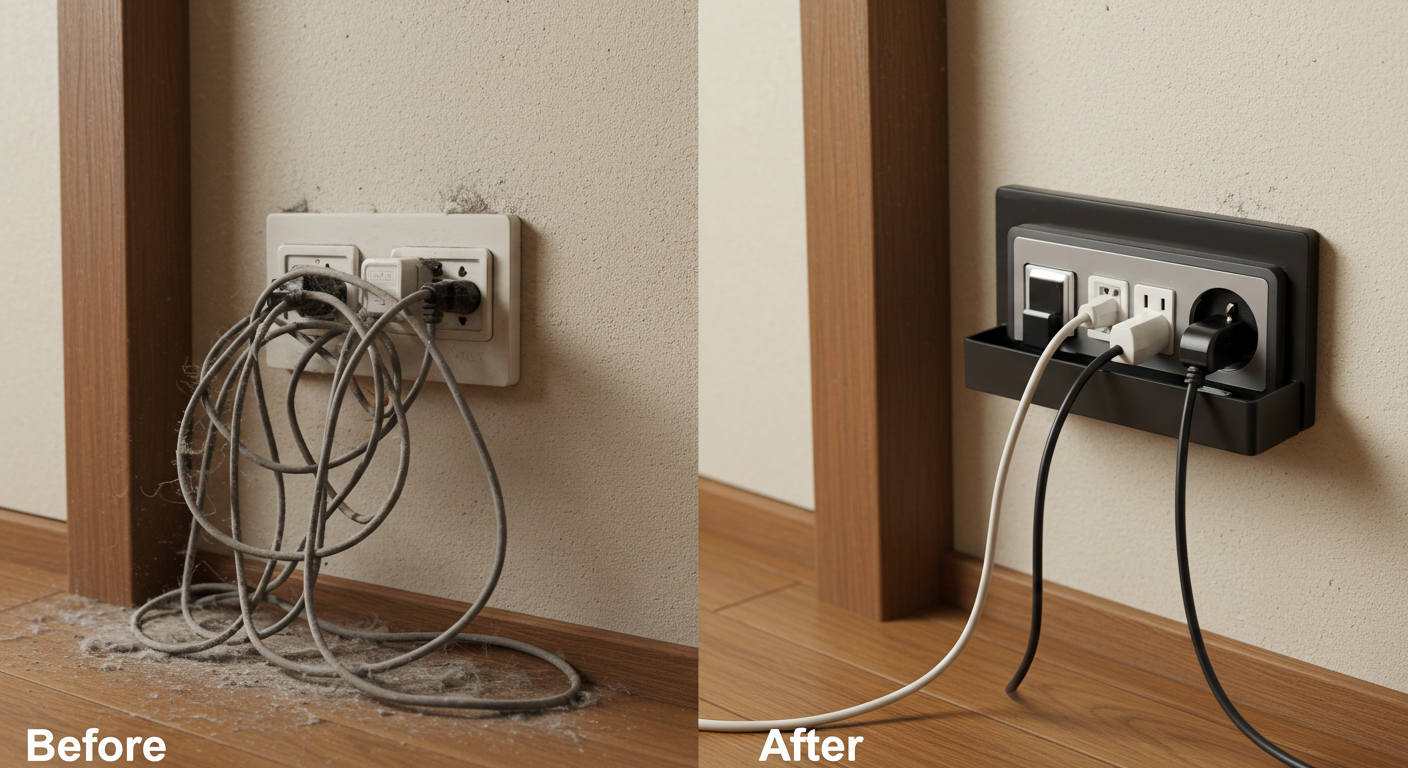「うちのマンションは鉄筋コンクリート造りだから、火事になっても燃え広がりにくいし安心だ」
もし、あなたが心のどこかでそう思っているとしたら、少しだけお時間をください。その「安心」は、時として最も危険な油断となり得ます。
一瞬にして日常を奪い去る火災は、決して他人事ではありません。特に、多くの世帯が壁一枚で暮らす集合住宅では、一つの火種が想像を絶する事態を引き起こす可能性があるのです。
この記事では、長年防災に携わってきた専門家として、そして地域社会の「助け合い」を支える共済組合の一員として、見過ごされがちなマンション火災の恐ろしさと、本当に重要な防火の心得について、独自の視点からお話しします。
読み終えたとき、あなたはきっと「知っておいてよかった」と感じるはずです。
「燃えにくい」という神話の落とし穴

確かに、マンションの構造体である鉄筋コンクリートは不燃性です。
しかし、それは「建物が燃え落ちない」というだけで、「室内が燃えない」という意味ではありません。
私たちの暮らしは、カーテン、ソファ、衣類、書籍といった実に多くの可燃物に囲まれています。一度火がつけば、あっという間に室内は炎と危険なガスで満たされてしまうのです。
火災で命を落とす原因の多くは、実は炎による火傷ではなく、煙や有毒ガスを吸い込むことによる窒息や中毒です。
特に恐ろしいのは、煙が驚くべき速さで上階へと拡散していくこと。階段やエレベーターシャフトが煙突のような役割を果たし、たとえ火元から遠い部屋にいても、あっという間に危険な状況に陥るのです。
ベランダが火の通り道になる危険性
あなたが安全だと思っているベランダも、火災時には火の通り道になることがあります。
上階の住人が捨てたタバコの火が、あなたのベランダに干してある洗濯物に燃え移る。あるいは、下の階の火災が窓を突き破り、ベランダを伝ってあなたの部屋に迫ってくる。
さらに見落としがちなのが、ベランダにある隣室との「隔て板」です。
ここは火災などの緊急時に破って避難するための「命の通路」ですが、物置代わりに使っているご家庭が少なくありません。
「うちだけは大丈夫」という油断が、自分と隣人の逃げ道を塞いでしまうことになるのです。
あなた一人の問題ではない「共同責任」という現実

戸建て住宅とマンションの火災で決定的に違う点、それは「被害が自分の部屋だけで収まらない」ということです。
もし、あなたの部屋から火を出してしまったら、どうなるでしょう。
炎や煙が隣の部屋や上の階に燃え広がる直接的な被害はもちろん、消火活動による「水濡れ被害」も深刻です。
消防車が放水した大量の水は、あなたの部屋の床を抜け、階下の部屋の天井から降り注ぎます。その結果、階下の住人の大切な家財道具や電化製品を台無しにしてしまうのです。
火災は、被害者であると同時に、意図せずして「加害者」にもなり得る。それが集合住宅に住む者の「共同責任」です。
「申し訳ない」という気持ちだけでは、隣人の失われた日常を取り戻すことはできません。
法律は守ってくれても、心は守れない
日本では「失火責任法」という法律があり、火元となった人に重大な過失がなければ、隣家への損害賠償責任は原則として免除されます。
しかし、法律があなたを守ってくれたとしても、「お隣さんの生活をめちゃくちゃにしてしまった」という心の負担や、その後のご近所関係はどうなるでしょうか。金銭的な問題以上に、精神的なダメージは計り知れません。
最強の防火対策は「ご近所付き合い」にあり

では、どうすればマンション火災のリスクに備えることができるのでしょうか。
火災報知器の設置や消火器の準備はもちろん重要です。しかし、私が最も大切だと考える、意外なようで最も効果的な防火対策があります。
それは「良好なご近所付き合い」です。
唐突に思われるかもしれませんが、これこそが私たちの掲げる「相互扶助(助け合い)」の精神の第一歩なのです。
例えば、日頃から挨拶を交わす関係であれば、火災の初期消火に協力してくれるかもしれません。
「最近、〇〇さんの姿を見ないけれど大丈夫かしら」と気にかけてもらうことが、万が一の事態の早期発見に繋がることもあります。
年に一度の防災訓練に積極的に参加することも、顔見知りを増やす絶好の機会です。誰がどこに住んでいるのか、どんな家族構成なのかを何となくでも知っているだけで、緊急時の避難や安否確認は格段にスムーズになります。
お互いを気遣う小さな意識の積み重ねが、コミュニティ全体の防災力を高める、最も確実な投資なのです。
まとめ

今回は、集合住宅における防火の新常識についてお話ししました。
鉄筋コンクリートという「神話」を信じず、室内や煙の危険性を正しく理解すること。
火災は「共同責任」。あなた一人の問題ではないと自覚すること。
日頃からの「ご近所付き合い」こそが、最強の防災対策であること。
これらの心構えを持つことが、あなたと大切な隣人の命と暮らしを守る第一歩です。
そして、どれだけ備えても起こってしまう「万が一」のために、最後の砦となるのが経済的な備えです。
私たち共済組合は、「一人は万人のために、万人は一人のために」という「相互扶助」の理念のもと、営利を目的とせず、組合員の皆様が少しずつ掛金を出し合って、もしもの時に助け合う仕組みを運営しています。
手頃な掛金で、火災はもちろん、自然災害など幅広いリスクに備えることができます。
自分のため、そして地域で暮らす仲間のために、賢い備えを始めてみませんか。
それは、安心な未来への、最も確かな一歩となるはずです。