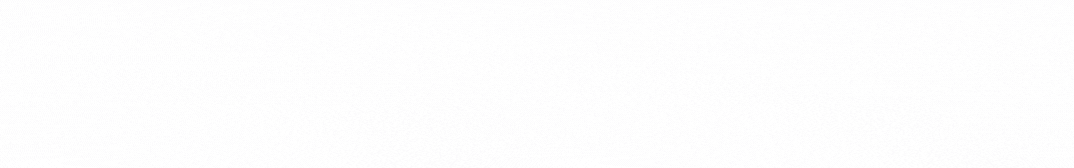皆さん、こんにちは! さっぽろ市民共済のブログライターです。
今年の夏は、本当にすごいことになっていますね。暦の上ではとっくに秋なのに、なぜか毎日クーラーが手放せない。「これって、本当に夏が終わったと言えるの?」と、誰もが一度は感じているのではないでしょうか。
今回は、そんな「夏の定義」にまつわる謎を、特にここ札幌の状況を交えながら深掘りしてみたいと思います。季節の移り変わりが曖昧になる中で、私たちはどうやって暮らしを守っていけばいいのか。一緒に考えていきましょう!
「夏」はいつからいつまで?誰もが納得する定義の難しさ

さて、まずは一番の疑問から。「夏」は、一体いつからいつまでなのでしょうか?
気象庁の定義は意外とシンプル
実は、気象庁が定めている夏の期間は、暦通りに決まっています。具体的には、「6月から8月」の3ヶ月間。これはいわゆる「気象学的季節区分」というもので、気温や気圧といった気象データに基づいて統計的に定められています。
しかし、今年の猛暑を考えれば、この定義に違和感を覚える人も多いでしょう。“体感”としては、9月も十分に夏ですよね。例えば、9月になっても30℃を超える日が続けば、誰だって「夏はまだ終わっていない」と感じます。
体感と暦のズレがもたらすもの
この“体感”と“暦”のズレは、私たちにさまざまな影響を与えます。例えば、衣服の準備。「もう秋だから」と薄手のセーターを出したものの、結局半袖で過ごす羽目に。食卓でも、秋の味覚を楽しもうと思っても、気分は冷たいそうめん。
このズレは、私たちの暮らしを単に不便にするだけでなく、健康面にも影響を及ぼします。熱中症は夏だけのもの、という思い込みが危険な事態を招く可能性も。
札幌の“夏”は変わったのか?気候変動のリアル

次に、今回のテーマの中心、札幌の「夏」に目を向けてみましょう。
“避暑地”だった札幌の異変
かつて、札幌は「避暑地」として知られていました。本州のうだるような暑さを逃れ、カラッとした涼しい夏を求めて多くの観光客が訪れました。しかし、近年、そのイメージは大きく変わりつつあります。
真夏日(最高気温30℃以上)や猛暑日(最高気温35℃以上)を記録する日が増え、熱帯夜(最低気温25℃以上)も珍しくなくなりました。これは、地球規模で進む気候変動の影響を、私たちが肌で感じている証拠です。
気象の変化にどう対応する?
気候が変化すれば、私たちの暮らし方も変えていかなければなりません。例えば、エアコンの普及率。これまで「エアコンなしでも過ごせる」と言われてきた北海道ですが、もはや必需品と言っても過言ではありません。
また、農業や漁業といった地域産業にも大きな影響が出始めています。季節の移り変わりが曖昧になることで、作物の収穫時期がずれたり、漁獲量に変動が生じたり。
これまでの常識が通用しなくなりつつある今、地域に暮らす私たち一人ひとりが、変化に気づき、柔軟に対応していく必要があります。
「新しい日常」としての“防災”を考える

最後に、この“曖昧な夏”の時代を生き抜くための、具体的な対策について考えていきましょう。
防災は“非常時”だけではない
これまでは、防災というと地震や台風といった“非常時”に備えるもの、という認識が一般的でした。しかし、気候変動が進む今、防災は“日常”の一部になりつつあります。
例えば、「もう9月だから大丈夫」と油断して、熱中症対策を怠ることは非常に危険です。水分補給や適度な休憩を心がけるといった、日々の体調管理も立派な防災です。
地域の“相互扶助”がカギ
そして、大切なのが「相互扶助」の精神です。特に高齢者や小さな子どもがいる家庭は、暑さに弱い傾向があります。
「近所のお年寄りが元気かな?」と一声かけること。「隣の子どもが遊びにきて、ちょっと暑そうにしていたら、冷たい麦茶をあげる」といった、日々の小さな助け合いが、地域全体の防災力向上につながります。
まとめ
今年の夏は、暦と体感のズレが私たちの暮らしに様々な影響を与えていることを改めて教えてくれました。特に札幌では、かつての“避暑地”というイメージが変わり、新たな気候への適応が求められています。
この変化の時代を生き抜くためには、「防災は日常である」という認識を持つことが重要です。そして、その日常の防災を支えるのが、私たち一人ひとりの「相互扶助」の精神です。
季節が曖昧になる中でも、地域で助け合い、支え合うことで、私たちはどんな変化にも対応できるはずです。これからの時代は、“個人”の力だけでなく、“地域”という大きな力で、安心して暮らせる社会を築いていきましょう。