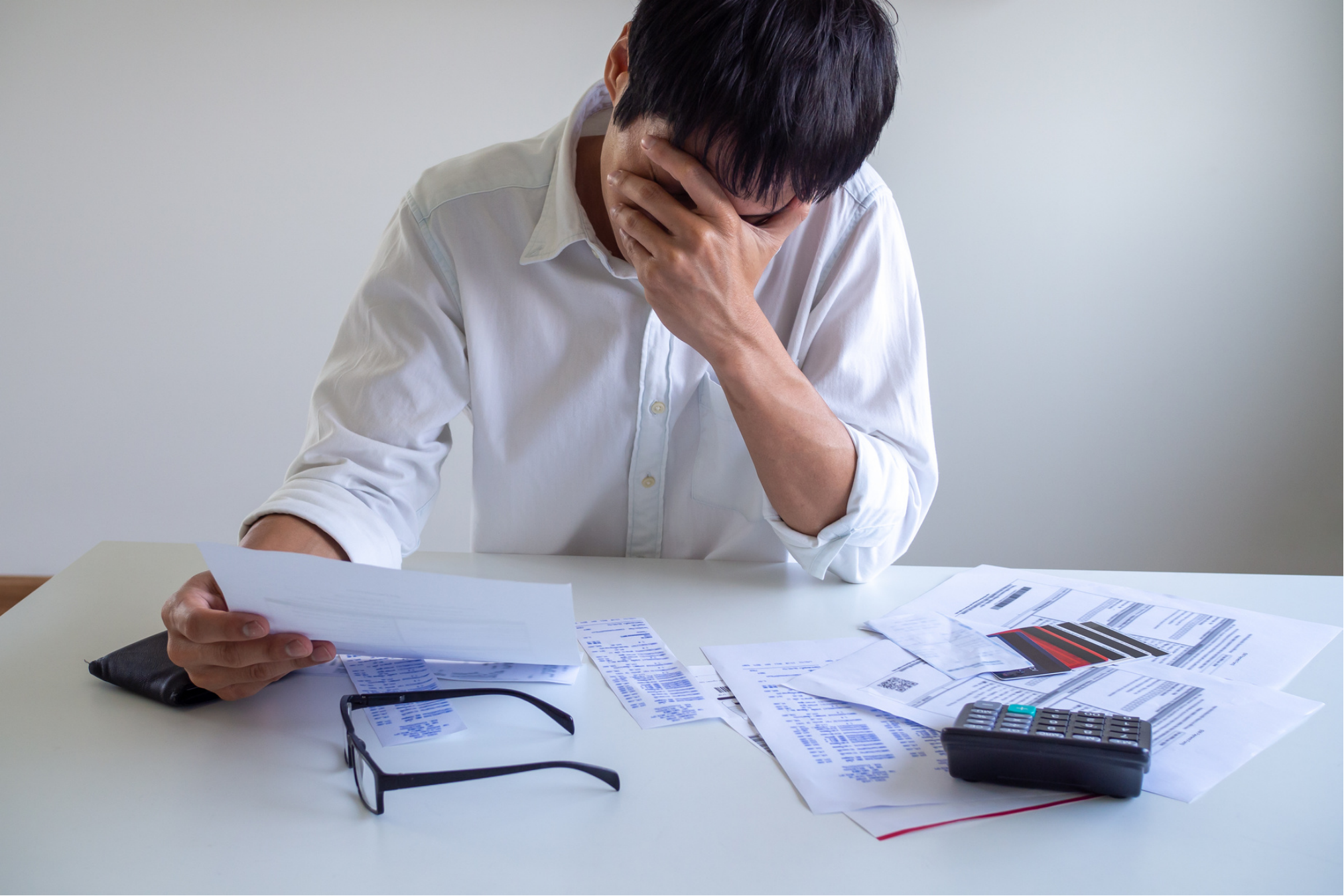火災共済の賢い選び方!「再取得価額特約」で家計を守る秘訣

皆さん、こんにちは!札幌市民共済ブログライターです。
突然ですが、もしもご自宅が火災に遭ってしまったら、どうしますか?想像するだけでも恐ろしいですが、日頃からの備えが何よりも大切です。特に、火災共済や火災保険といった「もしも」の時のための備えは、私たちの暮らしを守る上で欠かせません。
今回は、札幌市民共済の火災共済が誇る心強い特約、「再取得価額特約」に焦点を当てて、その賢い活用法を皆さんにお伝えしたいと思います。「再取得価額特約」という言葉、聞き慣れない方もいらっしゃるかもしれませんが、これを知っているか知らないかで、万が一の時に受けられる保障が大きく変わってくるんですよ。
なぜ「再取得価額特約」が重要なのか?

火災で建物や家財が損害を受けた際、共済金(または保険金)がどのように支払われるかご存知でしょうか?一般的な火災保険の支払い方式には、「時価額(じかかく)払い」と「再取得価額(新価:しんか)払い」の2種類があります。
「時価額払い」とは、火災で損害を受けた時点での建物や家財の価値を基準にして共済金が支払われる方式です。例えば、築20年の木造住宅が全焼した場合、その建物の「時価額」は新築時の価格から経年劣化分が差し引かれて算出されます。つまり、20年前の価値でしか保障されないため、実際に同じような家を建て直そうとしても、その費用には遠く及ばないという事態が起こり得るのです。せっかく共済に入っていても、これでは安心して家を再建できませんよね。
そこで登場するのが、今回ご紹介する「再取得価額特約」です。この特約が付帯されていれば、損害を受けた建物や家財を「新しく購入・修理するために必要な金額」、つまり「再取得価額(新価)」で共済金が支払われます。例えば、築20年の家が全焼しても、同じ構造、同じ規模の家を新築する費用が保障されるということです。家を建て直すとなると、土地代とは別に数千万円単位の費用がかかることも珍しくありません。この特約があるかないかで、ご自身の家計への負担が大きく変わってくるのは想像に難くないでしょう。
2. 火災共済の価値を最大限に活かす方法は「再取得価額特約」と付けることです!

これまで話してきたとおり、札幌市民共済の火災共済の価値を最大限に活かすための秘訣は、ズバリ「再取得価額特約」を付けることです。実は、「火災共済の加入基準額の70%以上で契約すること」で、この特約を自動的に付帯させることができます。
札幌市民共済では、建物の加入基準額を、専用住宅の場合「1坪(3.3㎡)あたり60万円」、併用住宅の場合「1坪(3.3㎡)あたり50万円」と定めています。
例えば、30坪の木造専用住宅にお住まいの場合を考えてみましょう。
建物の加入基準額:30坪 × 60万円/坪 = 1,800万円
この場合、「再取得価額特約」を付帯させるためには、建物の共済金額をこの1,800万円の70%以上、つまり1,260万円以上で契約する必要があるということです。
もし、1,260万円未満で契約してしまうと、残念ながら「再取得価額特約」は適用されません。その場合、万が一の火災時には「時価額払い」となり、実際に家を建て直す費用に足りない事態に陥る可能性があります。パンフレットの事例にもあるように、もし1,000万円の損害を被ったとして、再取得価額特約のあるAさんは1,000万円の支払いがあるのに対し、再取得価額特約のないBさんは、共済金額が加入基準額の70%未満だったため、約790万円しか支払われないといったケースもあります。これでは、残りの約210万円は自己負担となってしまい、家計に大きな打撃を与えてしまいます。
ご自身の建物の延床面積を確認し、上記の基準を参考に、適切な共済金額を設定することが非常に大切です。ご不明な場合は、お気軽に札幌市民共済の職員にご相談ください。
また、動産(家財)についても同様に、再取得価額特約が付帯される条件があります。動産の加入基準は世帯の居住人数によって異なります。
- 単身:500万円
- 2人:800万円
- 3人:1,100万円
- 4人以上:1,500万円
そして、建物と同様に、これらの「動産の標準加入額の70%以上」で契約することで、再取得価額特約が自動的に付帯されます。
札幌市民共済では、「相互扶助」の精神に基づき、組合員の皆様が安心して生活を再建できるよう、この「再取得価額特約」の付帯を推奨しています。地域に根ざした共済だからこそ、もしもの時に皆様が困らないよう、しっかりとした保障を提供したいと考えているのです。
見落としがちな落とし穴!知っておくべき「再取得価額特約」の注意点
「再取得価額特約」は非常に心強い特約ですが、いくつか注意すべき点があります。これらを知っておかないと、いざという時に「こんなはずじゃなかった!」と後悔することになりかねません。
3-1. 「時価額が再取得価額の50%以上」というもう一つの条件
実は、「再取得価額特約」が自動付帯されるための条件は、単に「共済金額が加入基準額の70%以上」であるだけではありません。もう一つ重要な条件として、「共済契約申込み当時の時価額が、再取得価額の50%以上であること」が挙げられます。
「時価額」とは、再取得価額から、建物の使用による消耗や経過年数に応じた減価額を差し引いた額のことです。つまり、建物が古すぎると、いくら加入基準額の70%以上で契約しても、再取得価額特約が付帯されない可能性があるということです。
例えば、築年数が相当経過した建物の場合、再取得価額は高くても、時価額が再取得価額の50%を下回ってしまうことがあります。このような場合、再取得価額特約は適用されず、共済金は時価額を基準に支払われることになります。
ご自身の建物の築年数や状態を考慮し、もし不安な場合は、札幌市民共済に相談して時価額の目安を確認してもらうことをお勧めします。
3-2. 他の保険や共済との重複に注意!
火災共済や火災保険に複数加入している場合、「重複契約」となり、共済金(保険金)の支払いに関して注意が必要です。
当組合の火災共済では、他の契約(保険、共済等)がある場合、原則として「共同査定は行わない」とされていますが、合計の共済金が損害額を超過しないよう、分担払いとなる可能性があります。つまり、複数の共済や保険に加入していても、実際に受け取れる共済金(保険金)の合計額は、実際の損害額が上限となるため、掛けすぎは無駄になる可能性があるのです。
現在加入している共済や保険の内容をしっかり確認し、保障が重複していないか、また「再取得価額特約」のような重要な特約が付帯されているかを確認しましょう。もし重複がある場合は、いずれかの契約を見直すことで、無駄な掛金を削減できる可能性があります。
3-3. 共済金が支払われないケースも知っておこう
どんなに手厚い保障があっても、共済金が支払われないケースも存在します。札幌市民共済の火災共済においても、以下のような事由で生じた損害に対しては共済金が支払われません。
- 契約者または共済金受取人の故意または重大な過失によって生じた損害
- 戦争、暴動、その他の変乱によって生じた損害
- 地震または噴火もしくはこれらによる津波によって生じた損害
- 風水害によって生じた損害
- 火災等に際し、共済の目的である物が紛失し、または盗難にかかったことによって生じた損害
特に、地震や噴火、津波、風水害といった自然災害による損害は、通常の火災共済の対象外となります。これらへの備えとしては、札幌市民共済が積み立てる「自然災害見舞金」制度がありますので、そちらも合わせて確認しておきましょう。


.png)