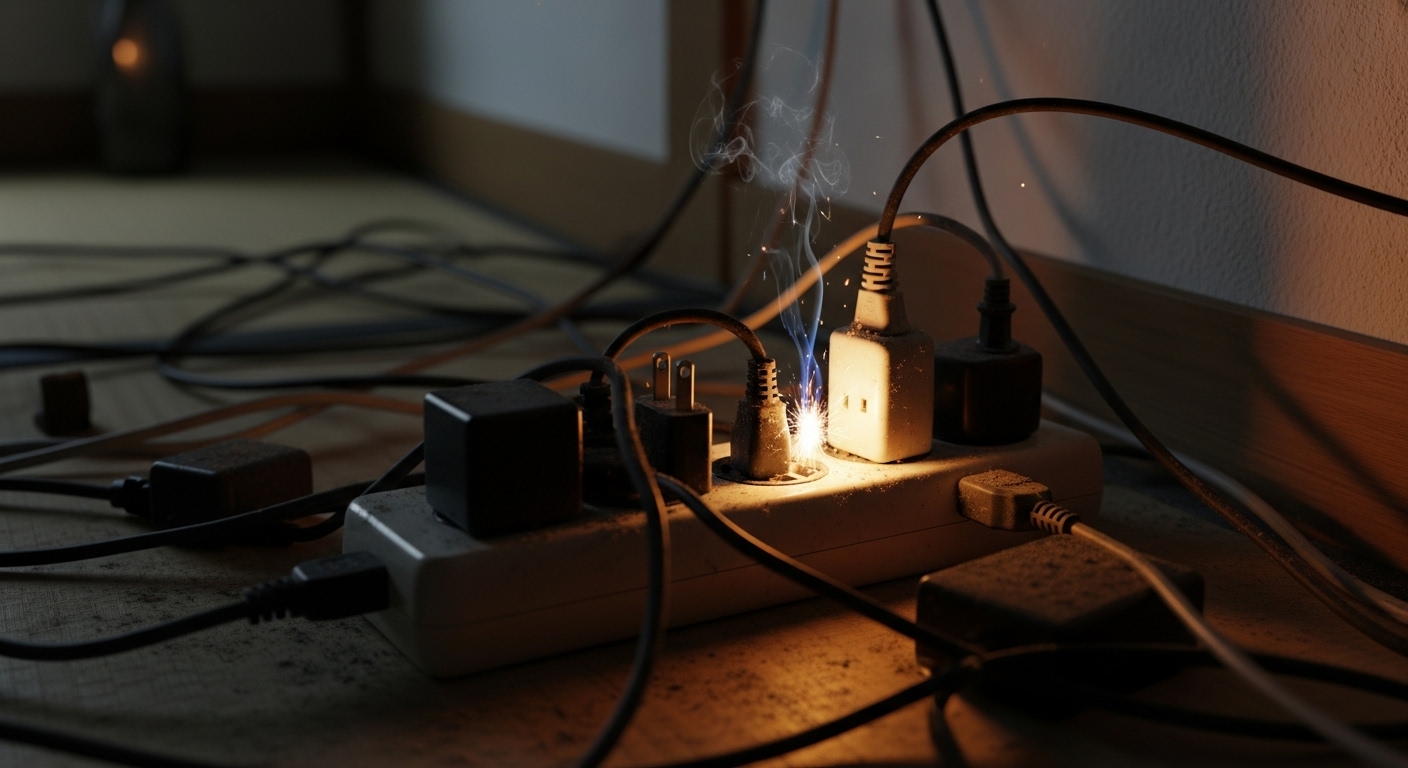令和7年の冬も、私たち北海道民にとっては厳しい季節となりました。電気代やガス代といった光熱費の高騰に加え、食料品や日用品の値上げも続き、家計のやりくりに頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。そんな中、意外と見落とされがちなのが、住まいの保障である「火災保険」や「火災共済」の掛金です。「契約した時のまま、何年も内容を見直していない」「保険料が高いけれど、安心のためだから仕方がない」もしそのように思われているなら、今こそ固定費を見直す絶好のチャンスかもしれません。私たち「さっぽろ市民共済」は、営利を目的とせず、地域のみなさまの“助け合い”で成り立っている生活協同組合です。今回は、札幌・石狩・小樽エリアにお住まいのみなさまへ、驚きの掛金で安心を手に入れる「火災共済」の魅力と、現代の生活リスクに備えるための賢い活用法について詳しくお話しします。驚きの低掛金!営利を目的としない「助け合い」の仕組みみなさまが一番気になるのは、やはり「掛金」のことではないでしょうか。さっぽろ市民共済の火災共済は、営利を目的としない相互扶助の精神で運営されているため、家計に優しい手頃な掛金を実現しています。例えば、建物の構造ごとの一口(保障額10万円)あたりの年間掛金をご覧ください。木造住宅:年額 80円(1口あたり)耐火住宅(マンション等):年額 40円(1口あたり)これは月額ではなく、「年額」です。具体的に、木造の戸建て住宅で2,000万円の保障(200口)を付けた場合を計算してみましょう。200口 × 80円 = 年間掛金 16,000円いかがでしょうか。この金額で、1年間、火災などの万が一の事態に備えることができるのです。さらに、私たち市民共済には「割戻金(わりもどしきん)」という嬉しい仕組みがあります。これは、毎年3月の決算で剰余金(余ったお金)が出た場合に、利用分量(掛金)に応じて組合員のみなさまにお戻しする制度です。もちろん、災害の発生状況や決算内容によっては割戻しがない年もありますが、これは「営利を追求せず、余剰金が出れば加入者に還元する」という、生協ならではの誠実な姿勢の表れです。「掛け捨てはもったいない」と感じている方にとっても、この仕組みは大きなメリットと言えるでしょう。古い家でも安心!「再取得価額」でしっかり建て直す掛金が安いと「保障内容は大丈夫なの?」と不安になる方もいらっしゃるかもしれません。ご安心ください。さっぽろ市民共済では、加入基準額の70%以上でご契約いただいた場合、「再取得価額特約」が自動的に付帯されます。これは、万が一火災で家が全焼してしまった場合に、その家が古くても、「同程度の家を新しく建て直すために必要な金額」をお支払いするというものです。時価額と再取得価額の違い一般的な保険では、建物の経年劣化分を差し引いた「時価額」しか支払われないケースがあります。例えば、2,000万円で建てた家が20年経って価値が半分になっていた場合、時価額では1,000万円しか支払われません。これでは、新しい家を建てるのに自己負担が大きくのしかかってしまいます。しかし、市民共済の「再取得価額」なら、現在の建築費に合わせて再び家を建てるための費用(限度額の範囲内)が支払われます。火災(消火活動による水漏れ・破壊含む)破裂・爆発航空機の墜落・物体の落下自動車の飛び込み落雷による衝撃・波及損害これらの事故しっかりカバーし、さらに「臨時費用共済金」や「残存物取片づけ費用共済金」など、再建時にかかる諸費用をサポートする費用共済金もプラスされます。“安かろう悪かろう”ではなく、“必要な保障を適正な価格で”提供するのが、私たちの誇りです。現代のリスクに備える「ハイブリッド」な保障スタイルここまで火災共済のメリットをお伝えしましたが、正直にお伝えしなければならない点もあります。それは、近年増加している「自然災害(台風・洪水・雪害)」や「地震」に対する保障についてです。さっぽろ市民共済の火災共済では、風水害や地震による損害は、共済金のお支払い対象外となっており、代わりにお見舞い金程度の「見舞金制度」で対応しています。しかし、近年の北海道における異常気象や地震リスクを考えると、これだけでは不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。そこで私たちがおすすめしているのが、「火災共済」+「補完火災保険」というハイブリッドな加入方法です。火災共済 補完火災保険(地震保険付き)の活用これは、ベースとなる火災などの保障を割安な「市民共済」で確保し、共済でカバーしきれない自然災害や地震、盗難などのリスクを、提携する損害保険会社の「補完火災保険」で上乗せするという方法です。ベースの火災保障:市民共済で安く抑える自然災害・地震:補完火災保険でしっかり備えるこの組み合わせにより、すべてを民間の保険会社で契約するよりも、トータルの保険料を抑えつつ、充実した保障を得られる可能性があります。特に、冬のスノーダクトの凍結やオーバーフローによる水漏れ事故は、自然現象(雪・氷)が原因とされる場合、通常の火災共済では対象外となることがあります。北海道特有のリスクに万全を期すためにも、ご自身のライフスタイルや予算に合わせて、最適な組み合わせをご検討ください。私たち窓口スタッフが、組合員様一人ひとりに寄り添い、無理のないプランをご提案させていただきます。まとめ今回は、さっぽろ市民共済の「火災共済」について、その掛金の安さと充実した保障内容、そして現代のリスクに対応する賢い加入方法をご紹介しました。営利を目的としない相互扶助だからできる「低掛金」古い家でも安心の「再取得価額」保障補完保険との組み合わせで「自然災害・地震」もカバー加入いただけるのは、札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、および小樽市にお住まいか、勤務先がある方です。加入時には組合員となっていただくため、出資金として10口100円をお預かりしますが、これは脱退時に全額お返しいたします。家計の負担を少しでも減らし、浮いたお金をご家族の笑顔や将来のために使っていただきたい。それが、私たちさっぽろ市民共済の願いです。「今の保険料、ちょっと高いかも?」と思ったら、ぜひ一度、お気軽に試算をご依頼ください。小さな負担で得られる大きな安心を、あなたとあなたの大切なご家族へお届けします。